「家族が借金を抱えている…。」そんな時、真っ先に頭をよぎるのは「もしかしたら、家族にも取り立てがくるかもしれない、借金の影響が及ぶかもしれない…」そう考えると、不安で夜も眠れないかもしれません。
しかし、ご安心ください。債務者の家族だからといって、必ずしも借金の責任を負うわけではありません。法律で、家族への取り立ては厳しく制限されています。
この記事では、債務者家族への取り立てに関する法律や、家族が借金で困った時の対処法をわかりやすく解説していきます。
また、借金問題を解決するための具体的なステップや相談窓口もご紹介しますので、ぜひ最後まで読んで、不安を解消してください。
- 債務者の家族だからといって、必ずしも借金の責任を負うわけではない。
- 法律で、家族への取り立ては厳しく制限されている。
- 債務整理など、借金問題を解決するための方法がある。
- 困った時は、一人で悩まずに専門の相談窓口に相談することが大切。
債務者家族への取り立てに関する不安を解消!家族への影響と対処法
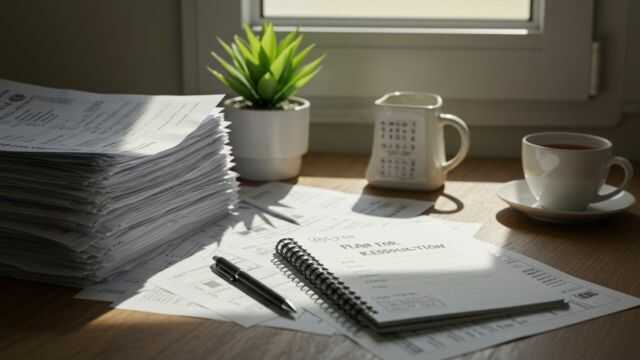
家族に借金の取り立ては来るのか?
「家族が借金を抱えてしまった…。」そんな時、真っ先に気になるのは「もしかして、家族にも取り立てが来るんじゃないか?」という不安ですよね。結論から言うと、保証人になっていない限り、家族に借金の取り立てが来ることはありません。
これは、貸金業法という法律で、借金の返済義務がない人に取り立てをすることが禁止されているからです。家族だからといって、本人に代わって借金を返す義務はありませんのでご安心ください。貸金業法第21条1項7号では、「債務者以外の者に対し、債務を弁済するよう要求すること」を明確に禁じています。
しかし、例外として、あなたが借金の連帯保証人になっている場合や、名義を貸している場合は、取り立ての対象になる可能性があります。 また、闇金業者から借金をしている場合は、違法な取り立てを受ける可能性があるので注意が必要です。
借金を家族に取り立てるのは違法?
前述の通り、貸金業法では、借金の返済義務がない家族に取り立てをすることは違法とされています。もし、家族が借金の取り立てを受けている場合は、すぐにでも金融庁や弁護士に相談しましょう。
法律を守って営業している消費者金融や銀行、クレジットカード会社などが、返済義務のない家族に取り立てを行うことはまずありません。しかし、ヤミ金業者は法律を無視して違法な取り立てを行うことがあるので、注意が必要です。ヤミ金業者は、貸金業法で定められた登録を行っていない違法業者であるため、法律の規制を受けません。そのため、家族や職場にまで連絡をしてくるなど、違法な取り立てを行う可能性があります。
もしヤミ金業者から借金をしてしまった場合は、決して返済に応じず、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
取り立てがやってはいけないことは?
借金の取り立てには、法律で厳しいルールが定められています。例えば、夜10時以降の取り立てや、大声で脅す行為、勤務先への連絡などは禁止されています。 具体的には、貸金業法第18条、第19条、第21条などに、取り立てに関する禁止事項が規定されています。
もし、このような違法な取り立てを受けている場合は、証拠を集めて警察に相談しましょう。録音や録画、写真などが証拠になります。
| 禁止されている取り立て行為 | 根拠法令 |
|---|---|
| 午後9時から午前8時までの間の電話や訪問 | 貸金業法第18条1項1号 |
| 債務者の勤務先への電話や訪問 | 貸金業法第18条1項2号 |
| 債務者以外の者への返済要求 | 貸金業法第21条1項7号 |
| 暴力的な言動や脅迫 | 貸金業法第21条1項1号 |
保証人じゃないのに取り立てはできる?
保証人になっていない場合、家族に借金の取り立てをすることはできません。ただし、ヤミ金業者は違法な取り立てを行うことがあるので注意が必要です。
また、家族が勝手にあなたの名前で借金をしてしまった場合(名義貸し)は、あなたに返済義務が発生する可能性があります。このような場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
債権回収会社は家族にも請求できる?
債権回収会社も、貸金業者と同じように、家族に借金の請求をすることはできません。ただし、債権回収会社の中には、違法な取り立てを行う悪質な業者も存在します。
もし、債権回収会社から不当な請求を受けた場合は、毅然とした態度で対応し、必要があれば弁護士や警察に相談しましょう。
家族の借金と縁切り
「家族が借金まみれで、もう縁を切りたい…。」そう思ってしまう気持ちも分かります。しかし、縁を切ったとしても、借金の返済義務からは逃れることはできません。
もし、あなたが連帯保証人になっている場合は、借金を返済する義務があります。また、相続が発生した場合には、借金も相続財産となるため、返済義務を負う可能性があります。
実家への取り立てについて
借金の取り立ては、債務者の自宅だけでなく、実家にも及ぶことがあります。特に、債務者が実家に住んでいる場合や、実家の家族が連帯保証人になっている場合は、実家への取り立てが行われる可能性が高くなります。
もし、実家が借金の取り立てを受けている場合は、債務者本人と協力して、借金問題の解決を図る必要があります。
家族への借金の連絡
借金があることを家族に知られたくないと思う人は多いでしょう。しかし、借金問題を解決するためには、家族に相談することも大切です。
家族に相談することで、精神的な負担を軽減できるだけでなく、経済的な支援を受けられる可能性もあります。また、家族の協力があれば、債務整理などの手続きもスムーズに進めやすくなります。
債務者家族の法的知識と解決策

家族の借金と死亡
家族が借金を残して亡くなった場合、その借金は相続財産となります。相続が発生した場合、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続することになります。
もし、借金を相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きを行うことができます。相続放棄をすれば、借金を相続せずに済みます。ただし、相続放棄には期限があるため、注意が必要です。相続放棄は、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することで行うことができます。
相続放棄の期限は、原則として、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内です。
兄弟の借金と支払い義務
兄弟が借金をしていても、あなたがその借金の連帯保証人になっていない限り、支払い義務はありません。
しかし、兄弟があなたの名前で借金をした場合や、あなたが兄弟の借金の連帯保証人になっている場合は、支払い義務が発生する可能性があります。
子供の借金と親への連絡
子供が借金をしていても、親に支払い義務はありません。ただし、子供が未成年の場合は、親に連絡が行く可能性があります。
また、子供が親の名前で借金をした場合や、親が子供の借金の連帯保証人になっている場合は、親に支払い義務が発生する可能性があります。
消費者金融と家族の支払い義務
消費者金融から借金をしていても、家族に支払い義務はありません。ただし、家族が連帯保証人になっている場合は、支払い義務が発生する可能性があります。
また、ヤミ金から借金をしている場合は、家族にも違法な取り立てが行われる可能性があるので注意が必要です。
家族の借金の調べ方
家族が借金をしているかどうかを調べるには、信用情報機関に開示請求をするという方法があります。信用情報機関には、個人の借入状況などの情報が記録されています。
開示請求をすれば、家族がどこの金融機関からいくら借金をしているのかを知ることができます。ただし、開示請求をするには、本人の同意が必要となります。
主な信用情報機関としては、以下の3つがあります。
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- KSC(全国銀行個人信用情報センター)
借金問題解決のための相談窓口
借金問題で悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、専門の相談窓口に相談することをおすすめします。
相談窓口では、借金問題の解決方法や債務整理などの手続きについて、無料で相談することができます。主な相談窓口としては、以下のようなものがあります。
- 弁護士会
- 司法書士会
- 国民生活センター
- 法テラス
まとめ

今回は、「債務者家族への取り立て」について解説しました。
借金は、本人だけでなく、家族にも大きな影響を与える可能性があります。もし、家族が借金で悩んでいる場合は、早めに相談することが大切です。
この記事が、借金問題で悩んでいる方の参考になれば幸いです。
記事のまとめ
- 家族が借金をしていても、保証人になっていない限り、家族に取り立てが来ることはない
- 貸金業法で、借金の返済義務がない家族に取り立てをすることは禁止されている
- ヤミ金業者は、家族や職場にも違法な取り立てを行う可能性があるので注意が必要
- 夜10時以降の取り立てや、大声で脅す行為、勤務先への連絡などは禁止されている
- 家族が勝手にあなたの名前で借金をした場合(名義貸し)、あなたに返済義務が発生する可能性がある
- 債権回収会社も、家族に借金の請求をすることはできない
- 縁を切ったとしても、借金の返済義務からは逃れることはできない
- 家族が借金を残して亡くなった場合、その借金は相続財産となる
- 借金を相続したくない場合は、「相続放棄」という手続きを行うことができる
- 兄弟が借金をしていても、あなたが連帯保証人でない限り、支払い義務はない
- 子供が借金をしていても、親に支払い義務はない
- 借金問題で悩んでいる場合は、一人で抱え込まずに、専門の相談窓口に相談することが大切
この記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスを提供するものではありません。具体的な法的問題については、弁護士または司法書士などの専門家にご相談ください。
