「身内が亡くなったと思ったら、多額の借金が残っていて、しかも自分は連帯保証人になっていた…」
突然の訃報に際し、残された家族が故人の借金問題に直面することは少なくありません。特に、故人が生前に借金の連帯保証人になっていた場合、残された家族は大きな不安を抱えることになります。
債務者が死亡した場合でも、連帯保証人の責任は消滅するのでしょうか?また、時効によって債務を免れることはできるのでしょうか?
この記事では、債務者死亡後の連帯保証人の責任と時効について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。
相続放棄や時効の援用など、連帯保証人が取るべき対策についても解説しているので、ぜひ最後まで読んで、今後の対応にお役立てください。
- 債務者死亡後も連帯保証人の責任は消滅しない。
- 連帯保証債務には時効があり、時効期間は債権の種類によって異なる。
- 時効が成立するには、要件を満たし、時効の援用を行う必要がある。
- 連帯保証人が死亡した場合は、相続人が保証債務を相続する。
債務者死亡、連帯保証人、そして時効について

連帯保証人の債務はどうなる?債務者死亡と時効の関係
「身内が亡くなったと思ったら、多額の借金が残っていて、しかも自分は連帯保証人になっていた…」
そんな悩みをお持ちのあなたもいるかもしれません。債務者が死亡した場合、残された連帯保証人はどうなるのでしょうか?また、時効は適用されるのでしょうか?
この章では、債務者死亡後の連帯保証人の責任と時効について、より詳しく解説し、あなたの不安を解消していきます。
債務者死亡後、連帯保証人はどうなるのか?
結論から言うと、債務者が死亡しても、連帯保証人の責任は消滅しません。
なぜなら、連帯保証契約は、債務者と連帯保証人が債権者に対して独立して債務を負う契約だからです。債務者が死亡しても、連帯保証人としての契約関係は継続し、債権者は連帯保証人に対して債務の全額を請求することができます。
具体例として、AさんがBさんから100万円を借り入れ、Cさんが連帯保証人となったケースを考えてみましょう。Aさんが死亡した場合、BさんはAさんの相続人に対して100万円の請求をすることができます。しかし、相続人が相続放棄をした場合や、相続人が債務を返済できない場合は、BさんはCさんに対して100万円の請求をすることができます。
このように、連帯保証人は債務者と同様に債務を負う責任があるため、債務者が死亡した場合でも、その責任から逃れることはできません。
連帯保証人の債務の時効期間は?
連帯保証人の債務にも時効は存在します。時効とは、一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。
連帯保証人の債務の時効期間は、原則として10年です。ただし、商事債権の場合には5年となります。
商事債権とは、商行為によって生じた債権のことです。例えば、会社が取引先から商品を仕入れた場合の代金債権や、銀行が顧客に融資した場合の貸金債権などが商事債権に該当します。
時効期間は、債権者が権利を行使できるようになった時から起算されます。例えば、返済期日が定められている債務の場合、最後の返済期日の翌日から時効期間が起算されます。
保証人が死亡した場合の時効は?
保証人が死亡した場合、その保証債務は相続人に引き継がれます。相続人が保証債務を相続した場合、時効期間は被相続人のもとで経過した期間と相続人のもとで経過した期間を合算して計算されます。
例えば、被相続人が保証人になってから3年間請求がなかった場合、相続人はその後7年間請求がなければ時効が成立します。
このように、保証人が死亡した場合でも、時効期間は引き継がれるため、相続人は注意が必要です。
時効成立の要件とは?
時効が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- 時効期間が経過していること
- 時効の更新(中断)事由がないこと
- 時効の援用
時効期間が経過していることは、前述の通りです。
時効の更新事由とは、時効の進行を中断させる事由のことです。例えば、債権者が裁判を起こしたり、債務者が債務を承認したりすることなどが時効の更新事由に該当します。
時効の援用とは、債務者が債権者に対して時効が成立したことを主張することです。時効の援用は、口頭でも行うことができますが、後日のトラブルを避けるため、書面で行うことが推奨されます。
主債務者死亡の場合
主債務者が死亡した場合でも、連帯保証人の債務は消滅しません。主債務者の相続人が債務を相続した場合、連帯保証人は相続人に対して債務の履行を請求することができます。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、債務は相続されません。この場合、連帯保証人は債権者に対して債務を返済する義務を負います。
連帯保証人が複数いる場合
連帯保証人が複数いる場合、それぞれの連帯保証人に対して時効期間が進行します。例えば、AさんとBさんが連帯保証人になっている場合、Aさんに対して時効が成立しても、Bさんに対しては時効が成立しないということがありえます。
また、連帯保証人の一人が債務を承認した場合、その連帯保証人に対しては時効が中断されますが、他の連帯保証人に対しては時効が中断されません。
債務者死亡、連帯保証人の相続と時効
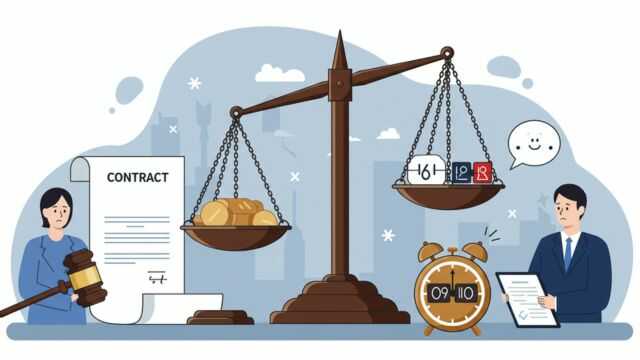
連帯保証人死亡で保証は解除される?
連帯保証人が死亡した場合、保証は解除されません。連帯保証人の債務は、相続人に引き継がれます。
相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。これは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務も含まれるということです。
連帯保証人の債務も、相続の対象となる債務の一つです。そのため、連帯保証人が死亡した場合、その相続人は、被相続人の連帯保証債務を承継することになります。
連帯保証人死亡後の債務はどうなる?
連帯保証人が死亡した後、その債務は相続人に引き継がれます。相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて債務を負担することになります。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者が1/2、子供がそれぞれ1/4ずつ債務を負担します。
相続人は、相続放棄をすることで、連帯保証債務を承継することを避けることができます。しかし、相続放棄をすると、プラスの財産も相続できなくなるため、注意が必要です。
父親が連帯保証人で死亡した場合
父親が連帯保証人で死亡した場合、その債務は相続人に引き継がれます。相続放棄をすれば債務を免れることができますが、相続放棄をすると父親のプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
父親が連帯保証人となっている債務があるかどうかは、父親の遺品や金融機関などに問い合わせることで確認することができます。
連帯保証人死亡、相続放棄はできる?
連帯保証人が死亡した場合でも、相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、連帯保証債務を免れることができます。
ただし、相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄申述書には、相続放棄をする理由などを記載する必要があります。
故人が連帯保証人だったことを知らなかった場合
故人が連帯保証人だったことを知らずに相続してしまった場合でも、相続放棄をすることができます。
ただし、相続放棄をするには、故人が連帯保証人だったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。
また、相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄申述書には、相続放棄をする理由などを記載する必要があります。
連帯保証人が死亡、債務はバレる?
連帯保証人が死亡した場合、債権者は相続人に債務の支払いを請求することができます。そのため、債務がバレる可能性はあります。
ただし、相続放棄をすれば債務を免れることができます。
また、債務がバレることを防ぐためには、債権者に対して、相続人が相続放棄をする旨を通知する必要があります。
債務者死亡、連帯保証人は相続人に?
債務者が死亡した場合、連帯保証人は相続人に対して債務の支払いを請求することができます。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、債務は相続されません。この場合、連帯保証人は債権者に対して債務を返済する義務を負います。
連帯保証人の相続放棄はできない?
連帯保証人の相続放棄は可能です。相続放棄をすれば、連帯保証債務を免れることができます。
ただし、相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄申述書には、相続放棄をする理由などを記載する必要があります。
連帯保証人が死亡、相続放棄はできる?
連帯保証人が死亡した場合でも、相続放棄をすることができます。相続放棄をすれば、連帯保証債務を免れることができます。
ただし、相続放棄をすると、被相続人のプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。相続放棄申述書には、相続放棄をする理由などを記載する必要があります。
まとめ

今回は、債務者死亡後の連帯保証人の責任と時効について解説しました。
債務者が死亡しても連帯保証人の責任は消滅しないこと、時効が成立するためには一定の条件を満たす必要があることなどを理解しておきましょう。
また、連帯保証人が死亡した場合、相続放棄をすることで債務を免れることができます。ただし、相続放棄をするとプラスの財産も相続できなくなるため注意が必要です。
この記事が、債務者死亡後の連帯保証人の責任と時効について悩んでいる方の参考になれば幸いです。
記事のまとめ
- 債務者が死亡しても連帯保証人の責任は消滅しない
- 連帯保証人の債務にも時効はある
- 時効期間は、債権の種類や債権者が権利を行使できることを知った時期によって異なる
- 時効が成立するには、時効期間の経過、時効の更新事由がないこと、時効の援用が必要
- 主債務者が死亡した場合でも、連帯保証人の債務は消滅しない
- 連帯保証人が複数いる場合、それぞれの連帯保証人に対して時効期間が進行する
- 連帯保証人が死亡した場合、保証債務は相続人に引き継がれる
- 相続人は、相続放棄をすることで保証債務を免れることができる
- 故人が連帯保証人だったことを知らなかった場合でも、相続放棄をすることができる
- 連帯保証人が死亡した場合、債務がバレる可能性がある
- 債務者死亡後、連帯保証人は相続人に対して債務の支払いを請求できる
